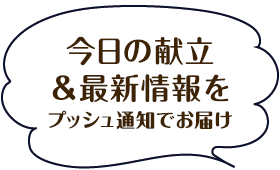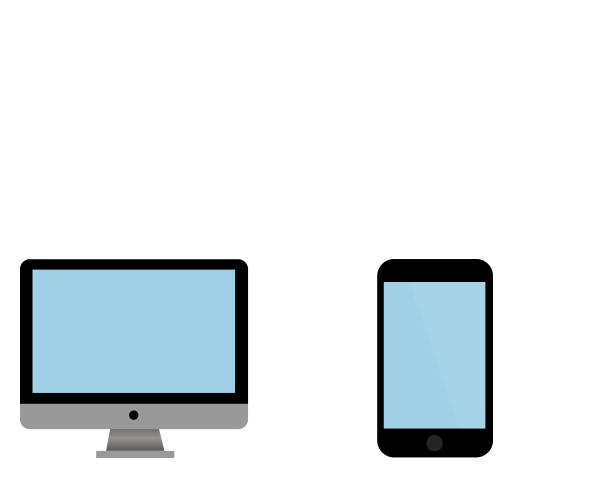ウインナーとソーセージはどう違う?日本と関係が深かった!種類も解説
2020年8月13日 11:00
お弁当やオードブルでは欠かせないソーセージ。ウインナーと言われることもありますよね。
両方とも同じようなもの、と思っていませんか?
実はこの2つには、違いがあるのです。しかし、はっきりとした違いを言える人は、あまりいないのではないでしょうか。
お弁当に入っているものは、ウインナーとソーセージ、どちらなのでしょう。また、お祭りの屋台で売られている「フランクフルト」の正体は?
今回は、ウインナーとソーセージの違いをご紹介いたします。これを機会にはっきりさせて、すっきりしましょう!

とはいえ、難しいことはなくしっかりした決まりがありますので、ご紹介していきます。
・ウインナーはソーセージの一種
ウインナーの正式名称はウインナーソーセージと言い、ソーセージの中の1タイプ、という位置づけになります。
ソーセージは世界中で1,000種類以上あると言われており、国によって材料や作り方など様々なものがあります。
・ソーセージとは

塩漬けされた豚肉や牛肉などを細かく挽いて、スパイスなど混ぜこみます。
それを動物や人工の腸に詰めた後に、茹でたり燻煙などの加熱処理をしたものを「ソーセージ」と言います。
「塩漬けされた」という意味のラテン語、「salsus」(サルサス)から取られたことが語源となっているそうです。語源に関しては諸説ありますが、上の説が最も有力とされています。
日本では、ケーシングといわれる皮の部分と太さで呼び名が変わってきます。中身の肉の種類で呼び名が変わることはありません。
では、代表的なソーセージの種類をご紹介いたします。
・ウインナーとは?JAS規格の基準
日本のJAS規格によると、羊の腸、もしくは人工的な腸に豚のひき肉を詰めたもので、大きさは直径20mm以内とされています。
ウインナーはソーセージの中でも一番小さいタイプになりますね。ウインナーの語源は発祥地である、オーストリアのウィーンから来ています。
現地ではウインナーと呼ばれてはいない…とのことなので、現地で頼むときは気を付けないといけないようです。

ウインナーがソーセージの1種だということはわかりましたが、ほかのソーセージはどのように分けられているのでしょうか。
・フランクフルトソーセージ
豚の腸、または人工の腸を使い、20mm~36mmの太さのものを言います。
ドイツのフランクフルトで発祥のソーセージのため、名称は地名からつけられました。つまり、ここで食べるソーセージは全て、フランクフルトソーセージということになります。
ドイツはソーセージの本場として有名で、それにはさまざまな背景があります。そもそも、ドイツでソーセージ文化が発達したのは、長い冬を乗り切るための保存食を作るためでした。冬になると餌がなくなり、家畜が死んでしまうため、さばいて保存食に加工しなければならないことが、ソーセージをつくるきっかけにもなったと言われています。
ほかにも、戦地に赴く兵士のために保存食を持たせるためでもありました。

・ボロニアソーセージ
牛の腸や人工の腸を使い、太さが36mm以上のものをさします。
イタリアのボローニャ地方発祥のソーセージで、イタリアでは「mortadella」(モルタデッラ)と言われています。前章に載せたソーセージの中では、一番太いソーセージになりますね。ソーセージと言いながらも、太さはほとんどハムと変わりません。
本場のイタリアでは豚肉のひき肉だけを使い、スパイスを混ぜてつくります。オリーブやピスタチオ、パプリカなども入ります。肉はクリーム状になるまで何度も挽いて、数時間から1日かけて茹でたりと、とても手間がかかるソーセージです。食べるときはハムのように、薄くスライスして食べることが多いです。
手間がかかっている分、味わいも深く、しっとりとした食感が楽しめるソーセージです。ウインナーやフランクフルトに比べると、あまりなじみがありませんが、普段の食卓からオードブルまで楽しめます。
・チョリソはウインナー?
チョリソーはもともとスペインが発祥の食べ物です。語源もスペイン語で「塩辛い」から来ています。また、ひき肉ではなく「細かくきざんだ肉」を使います。ウインナーと見た目はかなり似ていますが、材料や肉の加工方法、発祥は全く違うということになります。
チョリソーは赤いために、辛いソーセージのイメージがありますが、スペインで生まれた本来のものは、パプリカが入っているため赤く、辛くないのが特徴です。辛いソーセージと知られるきっかけとなったのは、メキシコの唐辛子入りのチョリソーが、スペイン発祥のチョリソーより先に日本に入ってきたからです。

ウインナーやソーセージは、主にヨーロッパが発祥の食べ物だということがお判りいただけたと思います。
しかし、今となっては日本の食卓には欠かせない食材となっていますよね。日本に根付くまでの歴史を見てみましょう。
・日本に伝わったのはいつ?
はっきりとした文献は残っていませんが、1910年にアメリカへ留学していた人物が食肉加工の講習会で発表しています。ほかにも、同じ時期に日本にいたドイツ人が、外国人向けのソーセージ店を営んでいたことから、この時期にはすでにソーセージは日本にあったと言えます。
このドイツ人はその後、戦争によって日本の捕虜になりそうでしたが許され、食肉加工のために貢献したと伝えられています。
・赤いウインナーは日本発
作られたのは昭和初期頃です。当時は肉の品質が悪く、おいしそうに見えなかったため、赤色で着色したのが始まりです。なんとも残念な理由ではありますが、お弁当のタコさんウインナーは赤いウインナーがなかったら、生まれていなかったかもしれません。
現在、赤いウインナーは海外でも、日本のオリジナルウインナーとして知られるようになりました。
・魚肉ソーセージも日本オリジナル

魚肉ソーセージは、大正時代に試験場で試作品を作ったことが始まりと言われています。現在、世界中でも魚肉ソーセージを見ることができますが、もともとは日本が発祥のソーセージなのです。
昭和30年代当時は、金額も高く庶民の食べ物には遠い存在でした。コロッケが1つ5円の時代に、魚肉ソーセージが130円もしたわけですから、かなりの高級品だったことがうかがえます。
ウインナーソーセージとほかの加工品の違いをご説明いたします。
・ウインナーソーセージとハムの違い

ハムは、豚のもも肉を塩漬けして、燻煙したものです。ウインナーソーセージはひき肉を加工して作りますが、ハムはかたまり肉をそのまま加工する、という点が違っています。
日本のハムにはロース部分を使った、ロースハムがありますが、世界的にハムと言ったらもも肉を使った、ボンレスハムのことをさします。また、ヨーロッパでは燻煙はせず、塩漬けした生の状態の物をハムと呼ぶことが多いです。
日本ではロース部分を使った「ロースハム」や肩部分を使った「ショルダーハム」など、部位によって種類が分けられています。それぞれ色味や食感が少しづつ変わってきますので、比べてみると面白いかもしれません。
・ウインナーソーセージとベーコンの違い
ベーコンは、豚のバラ肉を塩漬けして、低温で燻煙したものです。こちらもハムと同じで、ひき肉を加工するのか、かたまり肉を加工するのかの違いです。ベーコンは豚の「バラ肉」を使いますので、脂肪分が多くなります。
最終工程が燻煙になるので、香ばしさが残りますが塩分もそのままになります。一方、茹でる工程が最後になるウインナーソーセージは、塩分も低めに仕上がります。また、肉の食感も柔らかくなりますので、歯ごたえがあるベーコンとは全く違ったものになりますね。

ソーセージは国や地域によって形や原料が違っても、その土地オリジナルのものがつくられ、愛されていることがわかりました。
両方とも同じようなもの、と思っていませんか?
実はこの2つには、違いがあるのです。しかし、はっきりとした違いを言える人は、あまりいないのではないでしょうか。
お弁当に入っているものは、ウインナーとソーセージ、どちらなのでしょう。また、お祭りの屋台で売られている「フランクフルト」の正体は?
今回は、ウインナーとソーセージの違いをご紹介いたします。これを機会にはっきりさせて、すっきりしましょう!

©https://www.photo-ac.com/
目次 [閉じる]
■ウインナーとソーセージの違い
この2つの違いが、最もわかりづらいかもしれません。とはいえ、難しいことはなくしっかりした決まりがありますので、ご紹介していきます。
・ウインナーはソーセージの一種
ウインナーの正式名称はウインナーソーセージと言い、ソーセージの中の1タイプ、という位置づけになります。
ソーセージは世界中で1,000種類以上あると言われており、国によって材料や作り方など様々なものがあります。
・ソーセージとは

©https://www.photo-ac.com/
塩漬けされた豚肉や牛肉などを細かく挽いて、スパイスなど混ぜこみます。
それを動物や人工の腸に詰めた後に、茹でたり燻煙などの加熱処理をしたものを「ソーセージ」と言います。
「塩漬けされた」という意味のラテン語、「salsus」(サルサス)から取られたことが語源となっているそうです。語源に関しては諸説ありますが、上の説が最も有力とされています。
日本では、ケーシングといわれる皮の部分と太さで呼び名が変わってきます。中身の肉の種類で呼び名が変わることはありません。
では、代表的なソーセージの種類をご紹介いたします。
・ウインナーとは?JAS規格の基準
日本のJAS規格によると、羊の腸、もしくは人工的な腸に豚のひき肉を詰めたもので、大きさは直径20mm以内とされています。
ウインナーはソーセージの中でも一番小さいタイプになりますね。ウインナーの語源は発祥地である、オーストリアのウィーンから来ています。
現地ではウインナーと呼ばれてはいない…とのことなので、現地で頼むときは気を付けないといけないようです。
■ウインナー以外のソーセージの種類

©https://www.photo-ac.com/
ウインナーがソーセージの1種だということはわかりましたが、ほかのソーセージはどのように分けられているのでしょうか。
・フランクフルトソーセージ
豚の腸、または人工の腸を使い、20mm~36mmの太さのものを言います。
ドイツのフランクフルトで発祥のソーセージのため、名称は地名からつけられました。つまり、ここで食べるソーセージは全て、フランクフルトソーセージということになります。
ドイツはソーセージの本場として有名で、それにはさまざまな背景があります。そもそも、ドイツでソーセージ文化が発達したのは、長い冬を乗り切るための保存食を作るためでした。冬になると餌がなくなり、家畜が死んでしまうため、さばいて保存食に加工しなければならないことが、ソーセージをつくるきっかけにもなったと言われています。
ほかにも、戦地に赴く兵士のために保存食を持たせるためでもありました。

©︎https://o-dan.net/ja/
・ボロニアソーセージ
牛の腸や人工の腸を使い、太さが36mm以上のものをさします。
イタリアのボローニャ地方発祥のソーセージで、イタリアでは「mortadella」(モルタデッラ)と言われています。前章に載せたソーセージの中では、一番太いソーセージになりますね。ソーセージと言いながらも、太さはほとんどハムと変わりません。
本場のイタリアでは豚肉のひき肉だけを使い、スパイスを混ぜてつくります。オリーブやピスタチオ、パプリカなども入ります。肉はクリーム状になるまで何度も挽いて、数時間から1日かけて茹でたりと、とても手間がかかるソーセージです。食べるときはハムのように、薄くスライスして食べることが多いです。
手間がかかっている分、味わいも深く、しっとりとした食感が楽しめるソーセージです。ウインナーやフランクフルトに比べると、あまりなじみがありませんが、普段の食卓からオードブルまで楽しめます。
・チョリソはウインナー?
チョリソーはもともとスペインが発祥の食べ物です。語源もスペイン語で「塩辛い」から来ています。また、ひき肉ではなく「細かくきざんだ肉」を使います。ウインナーと見た目はかなり似ていますが、材料や肉の加工方法、発祥は全く違うということになります。
チョリソーは赤いために、辛いソーセージのイメージがありますが、スペインで生まれた本来のものは、パプリカが入っているため赤く、辛くないのが特徴です。辛いソーセージと知られるきっかけとなったのは、メキシコの唐辛子入りのチョリソーが、スペイン発祥のチョリソーより先に日本に入ってきたからです。
■ウインナーソーセージと日本の関係

©https://www.photo-ac.com/
ウインナーやソーセージは、主にヨーロッパが発祥の食べ物だということがお判りいただけたと思います。
しかし、今となっては日本の食卓には欠かせない食材となっていますよね。日本に根付くまでの歴史を見てみましょう。
・日本に伝わったのはいつ?
はっきりとした文献は残っていませんが、1910年にアメリカへ留学していた人物が食肉加工の講習会で発表しています。ほかにも、同じ時期に日本にいたドイツ人が、外国人向けのソーセージ店を営んでいたことから、この時期にはすでにソーセージは日本にあったと言えます。
このドイツ人はその後、戦争によって日本の捕虜になりそうでしたが許され、食肉加工のために貢献したと伝えられています。
・赤いウインナーは日本発
作られたのは昭和初期頃です。当時は肉の品質が悪く、おいしそうに見えなかったため、赤色で着色したのが始まりです。なんとも残念な理由ではありますが、お弁当のタコさんウインナーは赤いウインナーがなかったら、生まれていなかったかもしれません。
現在、赤いウインナーは海外でも、日本のオリジナルウインナーとして知られるようになりました。
・魚肉ソーセージも日本オリジナル

©https://pixabay.com/ja/
魚肉ソーセージは、大正時代に試験場で試作品を作ったことが始まりと言われています。現在、世界中でも魚肉ソーセージを見ることができますが、もともとは日本が発祥のソーセージなのです。
昭和30年代当時は、金額も高く庶民の食べ物には遠い存在でした。コロッケが1つ5円の時代に、魚肉ソーセージが130円もしたわけですから、かなりの高級品だったことがうかがえます。
■ウインナーソーセージと他の肉加工品
肉の加工品の代表格のソーセージのことは大体お判りいただけたと思います。ほかの加工肉はどのようにしてつくられるのかも、興味が出てきますよね。ウインナーソーセージとほかの加工品の違いをご説明いたします。
・ウインナーソーセージとハムの違い

©https://o-dan.net/ja/
ハムは、豚のもも肉を塩漬けして、燻煙したものです。ウインナーソーセージはひき肉を加工して作りますが、ハムはかたまり肉をそのまま加工する、という点が違っています。
日本のハムにはロース部分を使った、ロースハムがありますが、世界的にハムと言ったらもも肉を使った、ボンレスハムのことをさします。また、ヨーロッパでは燻煙はせず、塩漬けした生の状態の物をハムと呼ぶことが多いです。
日本ではロース部分を使った「ロースハム」や肩部分を使った「ショルダーハム」など、部位によって種類が分けられています。それぞれ色味や食感が少しづつ変わってきますので、比べてみると面白いかもしれません。
・ウインナーソーセージとベーコンの違い
ベーコンは、豚のバラ肉を塩漬けして、低温で燻煙したものです。こちらもハムと同じで、ひき肉を加工するのか、かたまり肉を加工するのかの違いです。ベーコンは豚の「バラ肉」を使いますので、脂肪分が多くなります。
最終工程が燻煙になるので、香ばしさが残りますが塩分もそのままになります。一方、茹でる工程が最後になるウインナーソーセージは、塩分も低めに仕上がります。また、肉の食感も柔らかくなりますので、歯ごたえがあるベーコンとは全く違ったものになりますね。
■ソーセージは世界中で愛される加工肉

©https://o-dan.net/ja/
ソーセージは国や地域によって形や原料が違っても、その土地オリジナルのものがつくられ、愛されていることがわかりました。
- ウインナーはソーセージの一種だった
- フランクフルトやボロニアソーセージは地名が由来の名称
- 赤いウインナーや魚肉ソーセージは日本のオリジナル
- 同じ肉でも加工方法で全く違うものになる
この記事もおすすめ

【今日の献立】2024年7月26日(金)「サバの竜田揚げ」
食コラム記事ランキング
- 1 ダイエット中の夜ご飯困ってない?500kcal以下の腸活メニュー7選~パスタやトーストも【太らない夜ご飯献立】
- 2 【7/23 ファミマ限定】八天堂とろけるくりーむパン「怪獣レモン」登場 ひんやりクリームがやみつきに!
- 3 コシが違う!本格「手打ちや冷やしうどん」の作り方〜冷やしうどんのアレンジレシピ10選も♪
- 4 【軽井沢から塩沢へ】昭和レトロな喫茶店とランチスポット4選~ジブリの洋館やジョン・レノン縁の珈琲店も
- 5 リーズナブルで簡単【サイコロステーキ】の作り方&レシピ5選~献立作りに役立つレシピも登場!
- 6 限定のサクレフレーバーは売り切れ前に要ゲット! 【最新コンビニアイス】セブン、ローソン、ファミマ3選
- 7 【ズッキーニ】人気レシピ40選~ナムルや炒め物、パスタやフライなど大人気レシピを調理法別にご紹介!
- 8 ダイエット中に中華なんて食べられるの?500kcal以下の中華メニュー7選【太らない夜ご飯献立】
- 9 「キュウリだけ」でできる超スピード料理人気レシピ14選 大量消費にも◎【材料1つで完成するおかず】
- 10 【今日の献立】2024年7月26日(金)「サバの竜田揚げ」
食コラム記事ランキング
最新のおいしい!
-
 塩もみキュウリのゴママヨ和え がおいしい!
塩もみキュウリのゴママヨ和え がおいしい!
ゲストさん 07:46
-
 焼きシシャモの甘酢漬け がおいしい!
焼きシシャモの甘酢漬け がおいしい!
ゲストさん 07:41
-
 牛肉の炒め物オニオンダレ がおいしい!
牛肉の炒め物オニオンダレ がおいしい!
ゲストさん 06:48
-
 万願寺唐辛子の肉詰め がおいしい!
万願寺唐辛子の肉詰め がおいしい!
ゲストさん 04:18
-
 ナス餃子 がおいしい!
ナス餃子 がおいしい!
ゲストさん 03:34
-
 焼きカボチャのサラダ がおいしい!
焼きカボチャのサラダ がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 ゆで卵のチーズパン粉焼き がおいしい!
ゆで卵のチーズパン粉焼き がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 コーンキャロット がおいしい!
コーンキャロット がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 しっとり柔らか 鶏むね肉のピカタ がおいしい!
しっとり柔らか 鶏むね肉のピカタ がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 サバの竜田揚げ がおいしい!
サバの竜田揚げ がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 さつま揚げと白菜の煮物 がおいしい!
さつま揚げと白菜の煮物 がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 シイタケと大葉のみそ汁 がおいしい!
シイタケと大葉のみそ汁 がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 塩もみキュウリのゴママヨ和え がおいしい!
塩もみキュウリのゴママヨ和え がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 ゴボウと油揚げの煮物 がおいしい!
ゴボウと油揚げの煮物 がおいしい!
ゲストさん 07/26
-
 サッパリ素麺サラダ がおいしい!
サッパリ素麺サラダ がおいしい!
ゲストさん 07/26
ウーマンエキサイト特集